さて、あれほど悪どくなんでもアリの手段を使い天下を取った家康が、
今度は手のひらをかえしたような改革をやります。
戦国の世で荒れ果て、血みどろに無法化した武士の文化を立て直してゆくのです。
素晴らしいね!
自分の覇権と繁栄しか目になかった信長や秀吉との、
決定的違いが、ここにあります。
荒れ果て情け無いほどに、道理も倫理も失い、ボロボロになってしまった武士のアイデンティティを、
儒教を導入して、ゼロから立て直してゆきます。
家康の功績については賛否さまざまにあると思いますが、
私が一番凄いと思うのが、この事です。
儒教を用いて武士の![]() 意識統一を
意識統一を
やり遂げていくのです。
儒教の教えに基づいて、仁、義、礼、智、信,と言うように、
武士として或いは人間としての生き方,心得が示されていきました。
まさに社会の根幹の思想と意識が、
明瞭にされているのです。
今まで野放しであった権謀術数や策謀や、下剋上や無礼極まる礼儀なしなどが通用しなくなる世の中に、
家康が変えてしまうのです。
信長や秀吉は、むしろアナーキーになる武士の意識を利用して、
彼らの個性に武将らをひれ伏せさせ自己覇権を図ったのですが、
これからの江戸は、リーダーたるもの自ら慎しみ深くあらねばなりません。
経済も、もちろん絶対的権力としての徳川幕府をひらきましたが、
各藩の自立を保障しました。
幕藩体制をとりながら、
武士の世の秩序を回復していきました。
関ヶ原の16年後に大阪冬の陣,そして夏の陣がおき、
ここで遂に豊臣政権は跡形もなく崩壊させられますが、
家康はその2年後に死んでしまいます。
考えられるのは、おそらく生前の頃から家康のその胸の裡に
豊臣政権崩壊後の新しい社会の統治をどうするかの青写真を、
相当緻密に練っていたのではないかと思います。
自分が死んでも,その後を継ぐ秀忠、
そして秀忠だけではなく、徳川幕藩体制が永遠に平和的に持続されるようなシステムや思想や方法論や法や社会規範を、
周到に準備していたのだと思います。
その具体策が
儒教文化を徹底的に普遍化していく事だったと思います。
子曰く〜と(し、のたまわく!)と
武士の師弟はまず論語を唱えながら勉強させられました…笑!
先に書きました儒学者の藤原惺窩、
朱子学の林羅山,
さらには法については南禅寺臨済宗の僧侶金地院宗伝など、
第一級の学者知者をブレインとして身辺に置き、
血みどろでデタラメ化した武士のアイデンティティを浄化し、
清新な武士社会を取り戻す為に。
そんなこと,信長も秀吉も、思いつきもしないでしょう。
なぜなら、彼ら二人ともがあまり学問や読書には興味が無かったし、
彼らは自分のエゴの為に天下を取ろうとしたのですから。
それに比べて家康は、社会の中に一本貫徹する秩序を引きました。
その結果、江戸の中には新しい武士道が花開いて行きましたね。
そして庶民の文化も花開いていきました…ヤレヤレ。
◯
ところがこの儒教に対して批判的な國學が,江戸中期から起こります。
そして江戸末期には國學を基に尊王思想が起き…アレアレ!
あの関ヶ原で腰抜け様であった毛利藩の中で、
ケンケンがくがくの論争が起き、
毛利は英国艦隊の圧倒的攻撃を受け、
尊王攘夷から開国へと開眼していきます。
毛利は家康の怒りを買い、領地の殆どを召し取られ現山口県の小さい藩に押し込められてしまいましたが、
もともとの学問好きと議論好きが高じてたくさんの人材が育っていきます。
ちなみ私も門司で生まれましたが
下関市長府町で育ち、
自分は小難しく理屈をこねる長州人だと思っています…笑
島津はさすが領地は召し取られずにすみましたが、
中央の情報に疎い日本一の田舎ものとしての嘲りを受けます、が。
逆にその汚名を返す如く日本中に密偵を配し、幕末には
大変な情報収集の藩になります。
ちなみに西郷隆盛はお庭方として、最終的には薩摩藩の情報収集の要役になります。
そしてこの二藩が、幕府を倒して行くのですから、
歴史は面白いねー。
兎にも角にもあの戦国の荒れ放題の時代から、江戸の太平の眠りの時代へと、
見事に家康が設計図を書いたと言う訳です。
つづく。



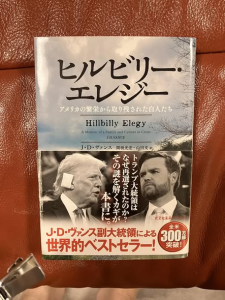
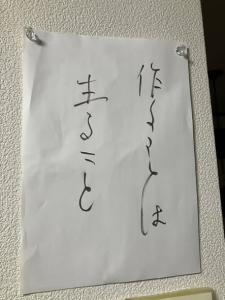
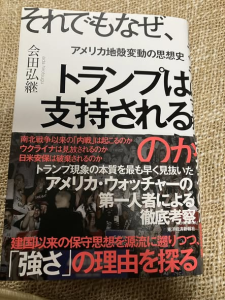


コメント